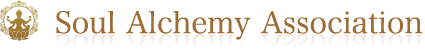御嶽行者の修行
修験道にはいろいろな宗派があります。密教系では本山派修験、当山派修験、金峯山修験、羽黒修験、英彦山修験など、ほかに神道系の修験、主人は神道御嶽教の「中座」でもあります。
中座とは御嶽山の神々やその他、いろいろな霊が降りてきて、そのお告げをします。かんたんに言うと霊媒師です。
この儀礼を御座といい、前座(霊をおろす人)と中座(おりてきた霊との取り次ぎをする人)が一組となっておこないます。
近年は独座といって、中座だけでやることも多いです。写真は主人の若いころで「中座ときの写真です」、髭も黒いです。今でも一連の神道儀式をするときは純色(白)の狩衣を着ます。
御座立ての儀礼は前座と中座という行者(神主)がコラボでおこなうわけですが、ここには重要な意味があります。
前座は祝詞をあげて神様をおろします。おりてきた神様の霊媒となって、神様からのメッセージを人間の言葉として伝えるのが中座です。
しかし、前座の役目は中座に憑依した神様(霊神)が本物であるかどうかを精査する役目もあります。
しかし御座立てのなかで独座というのは、中座が一人で前座と中座をやるわけです。つまりこの場合、中座はトランスに入りながら、トランスに入っている自身を冷静に見ることが必要になってきます。
中座の修行はインターバルトレーニングです。真冬の滝行を一日中、インターバルでやります。お堂で祝詞をあげて滝に入る、しばし休憩して、また同じことを繰り返す。これを一日に21回おこないます。
御嶽教(御嶽修験)の修行は滝行と、御嶽山頂への登山がメインですが、神道護摩も焚きます。これは密教の護摩とはまったくちがう作法と理念のもとに焚きます。
このビデオは御嶽山の三の池で、主人の祝詞に神楽鈴と太鼓をMIXしていますが、主人が神楽鈴を鳴らし、太鼓をたたきながら祝詞を唱えています。
7月でもまだ残雪があり、池の中にも凍った雪が残っています。御嶽山の山開きは7月初旬で御嶽行者はこの時期から登拝をはじめます。
冬の期間は行者装束ではとても寒くて登れませんから、冬に登るときは冬山登山の登山服でさらにテントやコンロ、食料など、なにかあったときのビバーク用具をザックに詰め込んで重装備で登ります。
もちろん地下足袋では足が凍傷になってしまいますので、重登山靴を履きます。雪山の御嶽山でも遭難さえしなれば日帰りで登れます。
さて御嶽行者は普段、なにをやっているかというと教会主管者や講元はご祈祷、各種の占い、霊神の供養です。